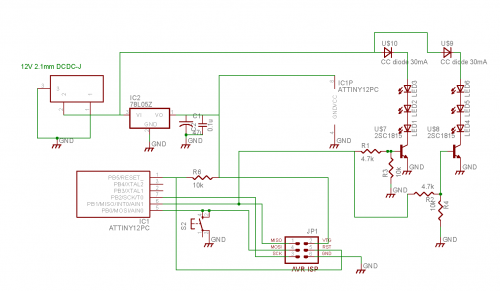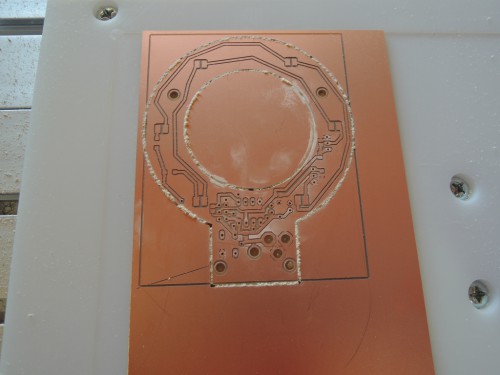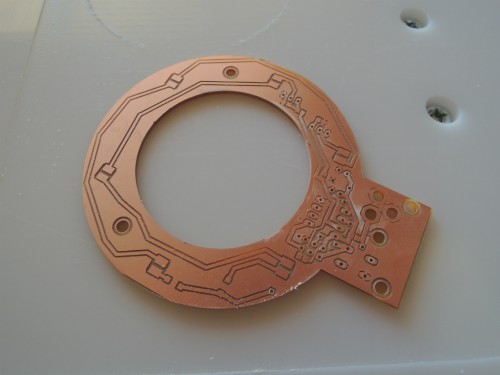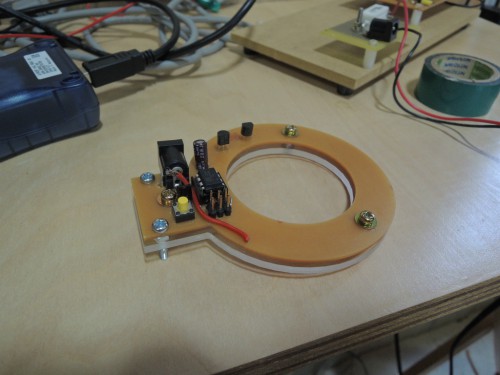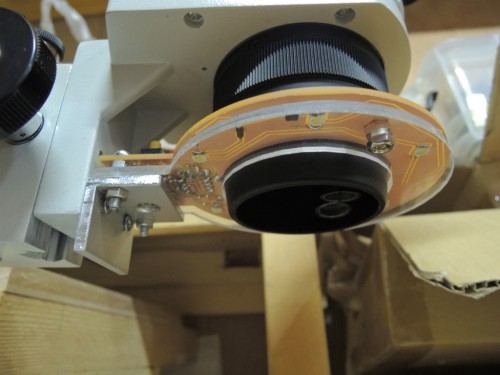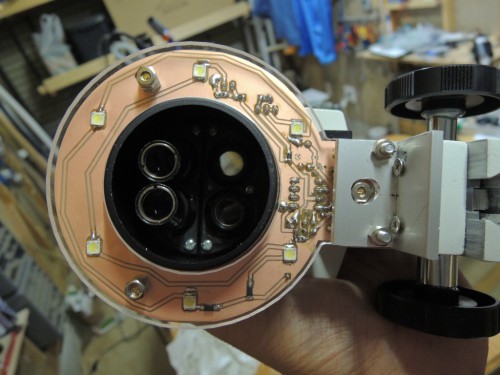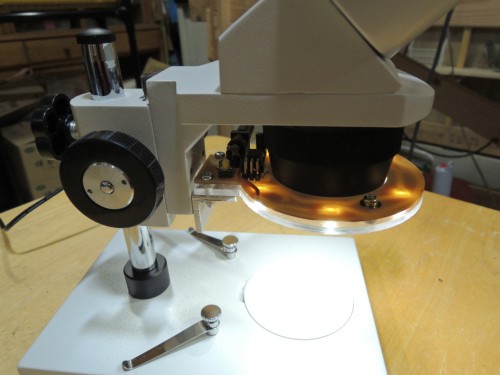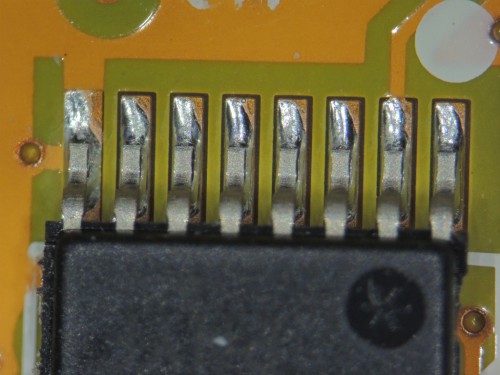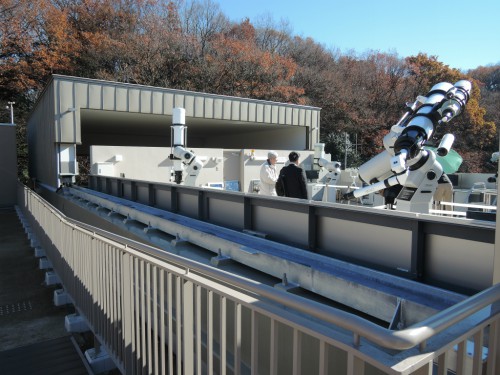今年もあと残すところ1日になりましたね。
仕事納めのあと、年末休みにようやく我が家のメンテナンスをできるチャンスが到来です。
共働きですとなかなか家の掃除が行き届きません。
窓掃除。できるだけまめにやりたいとは思うのですが、なかなかできず、約1年?半年ぶりにやりました。窓掃除は、我が家ではガラス用洗剤と窓ふきワイパーでやっていますが、なかなかすっきりいかないところもあり、もう少しいい道具があればなあなんて思いながらやっています。
一応、家の窓は1Fのはワイパーを1.5m程度伸ばしたら届くような感じ、2Fはどこも手で届くところに窓があるので、掃除が比較的楽で助かります。とか言って、1年に一回ぐらいしか掃除しないのだから、大変でも楽でも一緒?
窓は、畑に面しているところはやっぱり台風の時などに土が飛んでくるみたいでずいぶん土ぼこりがついてました。それから、我が家のまわりには、クモが結構いるので、住人がいないクモの巣がたくさん採取されました・・・もう少しまめに掃除したいところです。
もう一つ、なかなか掃除が行き届かないところということで、レンジフードの掃除をしました。レンジフード、お恥ずかしながら竣工以来一度も掃除をしていませんでした。
というわけで、掃除。掃除には、テレビで紹介されていた、「セスキ炭酸ソーダ」を使ってみました。ダイソーで100円でいっぱい買えます。同じくダイソーで雑巾と、スプレー瓶、それから手荒れをしないようにゴム手袋を買って、400円+税で、準備万端。
レンジフードのフィルターに積もった油混じりのホコリをセスキ炭酸ソーダ水にしばらくつけておくと、使い古しの歯ブラシで軽くこするだけで簡単に落ちました。
レンジフードのあちこちも、雑巾にセスキ炭酸ソーダをしみこませて拭くと簡単に溶けて油汚れが拭き取れます。すごいね。
というわけで、夢中で掃除をしてしまいました。フードも結局、シロッコファンのブレードまで分解して掃除してしまったし(これは失敗したかも。アルミはシミがついたりする可能性があるとのこと。油汚れは落ちても傷めたかな・・・)、目に付く油汚れがこびりついていそうなヤカンやら壁やらいろいろとセスキパワーで掃除をしました。
あとは、作った吊戸棚に地震の時扉が開かないようにロックをかけてくれる「感震くんⅡ」を取り付けたり、太陽熱温水器の配管に非粘着テープを巻いたりと、途中までやって放置していた家のあれこれを片づけているところ。飽きっぽいこともあって、結構そういう中途半端なのがたくさんあって大変です。今年は、あと一日ありますが、明日は台所や倉庫、外回りのコンセントを増設したり、倉庫の照明を増設したり、倉庫の壁を張り残したところを張ったりして終わるかなあ、という感じです。